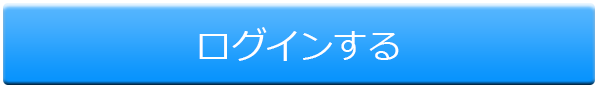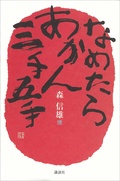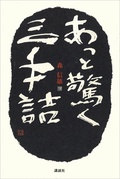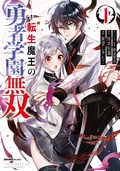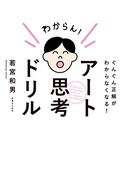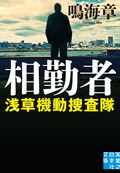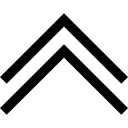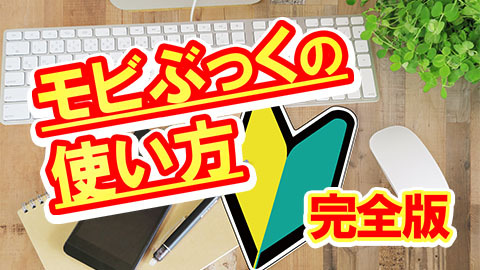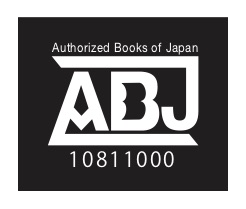詰むか詰まないか 読みきり将棋

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできません。
この本の特徴は以下の4点。
(1)どちらが詰むか詰まないか
一問でAとBがあり、どちらかが詰みどちらかが詰まない問題です。似たような形ですが、微妙に詰むか詰まないかの差が出てきます。詰むか詰まないかを答えると同時に、両方の問題の結論を読み切るのが「読みきり将棋」の特徴です。
(2)ボリュームたっぷりの出題
入門編50問、初級編60問、中級編49問の構成になっていて、問題数としてはその倍のボリュームがあり、詰むか詰まないかの答えを追求していく中で、終盤の読みの力を養うのがねらいです。
(3)詰む将棋と詰まない将棋を見極める
詰むか詰まないかの問題は、結論を出すまでに読みの量を増やす必要があります。詰ますパワーと同時に、詰まないのを読み切るパワーも身に付いてくるはずです。
(4)詰むときは駒余りも可
実戦に即しているので、駒余りも構いません。あくまで詰むか詰まないかを問う問題です。
以上の特徴を生かす上手な使い方は以下の4点です。
【1】詰むか詰まないか直感を試す
形を見て詰むか詰まないかの判断を下すときに、自分の中での直感はどちらか、それが大切です。直感は終盤の読みの総合力を計るバロメーターになります。
【2】詰むか詰まないかを読み切る
詰むか詰まないかの正確な答えを出すときはには、手を読み切るパワーが必要になります。詰むかつまないか不明のときに、自分の読みで結論をだすのは大きな自信につながるものです。直感から読みに転じて、しっかり向き合って下さい。
【3】正解を確認する
正解を確認するときは、自分の読みが合っていたかどうかが大事です。特に詰む結論のときは読みを間違えていないか、詰まない結論のときは読み以外の好手で詰まないか、その確認が大きな武器になります。
【4】一回でなくて何度か繰り返して解くのも大きいと思います。詰みそうで詰まない、詰まなさそうで詰む、それが本書のねらいです。繰り返して解くことによって、詰むか詰まないかを読み切る力を養って下さい。
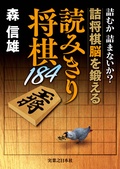
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端…
※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできません。
私は数えてみると延べ二百人くらいの子どもを相手に、ほぼ毎日のように直接指導やオンライン指導で指導対局をしています。
入門者からプロを目指す子どもまで、棋力の幅があるのでスイッチの切り替えが大変です。
駒落ちだけでなくて平手もいっぱい指していますが、終盤まで互角に戦う局面になる指し方、を心得としています。
自分の好みもありますが、中盤で決着がつくと物足りなく感じて、感想戦ではたいてい終盤の好勝負になだれこむように誘導しています。
もっとも強い子ども相手だと、そんな余裕はありません?
自分でも勝ちか負けかわからない局面が大好きです。模索する局面で、相手玉の詰みを発見すると何よりもうれしいし、自分の詰みを知るとがっかりです。
前著の「読みきり将棋」は入門から初中級レベルの内容でしたが、本書は「初級から上級」向けの出題です。
読みきり将棋というのは私の造語で、詰む問題と詰まない問題の二題をワンセットで出題して、詰む問題と詰まない問題を読み切るのがねらいです。
将棋の終盤で決着がつくのは、自玉や相手玉が詰むか詰まないか、その手段が見えてきた時です。
相手玉を詰まして勝つのが最良の勝ち方ですが、先に自玉が詰まされるとすかさず負けになります。
終盤の醍醐味はその前あたりがヤマ場になりますね。自玉も相手玉も詰むか詰まないかが見えにくい、相手よりも先にその見通しを立てるのが、終盤力の差といえます。
本書は徹底的に詰むか詰まないかの問題を追及して、終盤のパワーアップを目指した問題集です。
魅力ある終盤の世界に、自信を持って突入できる力を付けて下さい!
(著者まえがきより)…
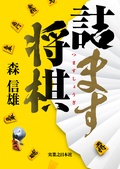
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端…
「どうして詰将棋は残りの持ち駒が全部なの?」子どもに訊かれてハッとしたのが今回の「詰ます将棋」を考えた発端です。確かに詰将棋と違って実戦で玉を詰ますときは、お互いの持ち駒が限定であり、駒余りも自然な筈です。そこに着目して考えたのですが、例えば玉方の持駒なしだと無重力のような?不思議な詰まし方に驚きもあります。初めは「詰む将棋」だったのですが、「詰め将棋」の誤植と思われそうなので「詰ます将棋」に変更しました。「詰ます将棋」は(1)詰将棋のジャンルの仲間としての存在感、(2)終盤の鍛錬としての武器、(3)楽しい感性のゲームとして、解いてもらえばと思います。私があれこれ考えた第1弾の「逃れ将棋」は王手の掛かった局面でどう逃れるかという問題でした。第2弾の「詰めろ将棋」は次に詰めろをかける、現在の詰めろを逃れる問題でした。今回のNEWジャンル第3弾は「詰ます将棋」で、玉を詰ますのが目的ですが、詰将棋のルールから、持ち駒限定、駒余り可に変更した問題です。読者の皆さんに、本書が楽しみながら終盤の棋力アップに役立つことを願っています。(著者まえがきより) ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできません。…

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端…
※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできません。
最果ての原野、断崖の景勝、人里離れた秘境、1日1便だけ、ギリギリの狭隘 etc.
乗れば旅情に浸れること間違いなし、珠玉の路線バスの旅へ!
未知なる土地への旅や地元の人とのふれあいなどが楽しめる、ローカル路線バスの旅がいま大人気です。その中でいま、ぜひ乗っておきたい100の路線を厳選。旅情あふれる紀行、旅心をそそる沿線の写真で構成、運行時間や便数や問い合わせ先などの諸データも充実した、読んで楽しく実用情報満載の一冊です。本書を手に、いざバス旅へ出かけよう!
■日本全国すみずみまで結ぶ、73社100路線カタログガイド
【北海道】宗谷バス/函館バス/沿岸バス/道南バス/ジェイ・アール北海道バス
【東北】岩手県北バス/JR東日本/羽後交通/秋北バス/下北交通
【関東】日本中央バス/西武観光バス/西東京バス/国際十王交通/都営バス/京浜急行バス/小鹿野町営バス/皆野町営バス/神奈川中央交通/富士急湘南バス/関東バス/新島村営バス
【中部】新潟交通観光バス/北鉄奥能登バス/若狭調整バス/伊那バス・中央アルプス観光/南木曾町営バス/栄和交通/大鉄アドバンス/日本平自動車/アルピコ交通/遠州鉄道バス/名古屋ガイドウェイバス/しずてつジャストライン
【近畿】三重交通/丹後海陸交通/奈良交通/京都バス/江若交通
【中国・四国】備北バス/両備バス/ウエスト神姫バス/井笠バスカンパニー/岡山電気軌道/宇野自動車/下津井電鉄/石見交通/平田生活バス/四国交通/瀬戸内運輸/サンデン交通/芸陽バス/三好市営バス/宇和島バス/瀬戸内海交通/四万十交通/高知東部交通
【九州】臼津交通/西日本鉄道/JR九州バス/長崎自動車/西肥自動車/さいかい交通/宮崎交通バス/高森町民バス/熊本バス/鹿児島交通/みなくるバス/産交バス/南国交通/西肥バス/西表島交通
■北海道から鹿児島まで、路線バス乗継ニッポン縦断(乗継データ集)
■エリア別・紹介バス路線のルートマップ

※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端…
新幹線でのアクセスで札幌・函館・道南へ。2016年3月26日に開業する、北海道新幹線。青函トンネルを走り抜けて、北の大地へいよいよ新幹線がやってきます。新たな北の玄関口となった新函館北斗駅から、函館と札幌・小樽、足をのばして富良野・美瑛、道南エリアへ、北の街と自然を歩くおさんぽガイドの決定版です! 巻頭特集では、新幹線でアクセスする北海道への旅を紹介。市電のループ化で市街の散歩が便利になった札幌の話題のスポット、新たに鉄道での北の玄関口となり変貌著しい函館、新函館北斗駅から近いネイチャーエリアの大沼公園など、新幹線を使っての新たな旅を提案します。地図ガイドは札幌と函館の市街を中心に、情報満載の地図で詳細にガイド。散策モデルコースに所要時間、アップダウンが示された地図で、楽々街を歩けます。もちろん、海鮮やラーメン、ジンギスカン、スープカレー、ローカルフードにスイーツといった各種グルメも充実。さらにランチやディナー、カフェなど、地元御用達の店もピックアップしています。ほかにも小樽、富良野に美瑛、旭山動物園、登別や洞爺、支笏湖など、周辺エリアの地図ガイドも盛りだくさん。これ1冊で、札幌と函館を起点にした旅が満喫できます。
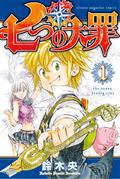 少年 | 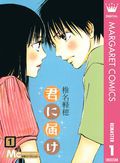 少女 |
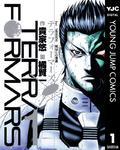 青年 |  大人向け |
 TL |  BL |